

ICU APOSTLES へのリンク

プロフィールgotoprofile.html へのリンク
著訳書リスト books.htm へのリンク
インナーーゲーム(研究会)へのリンク
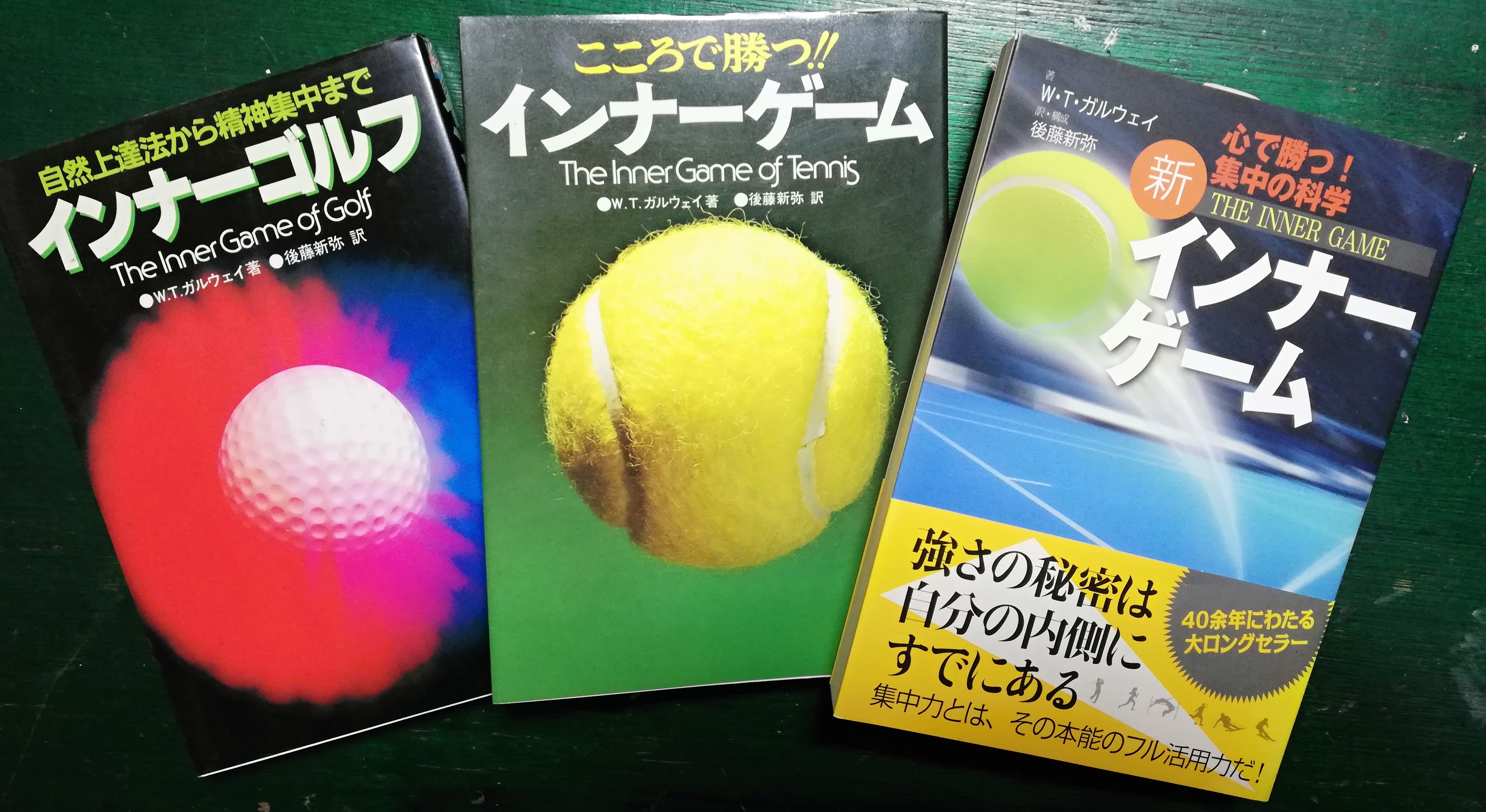



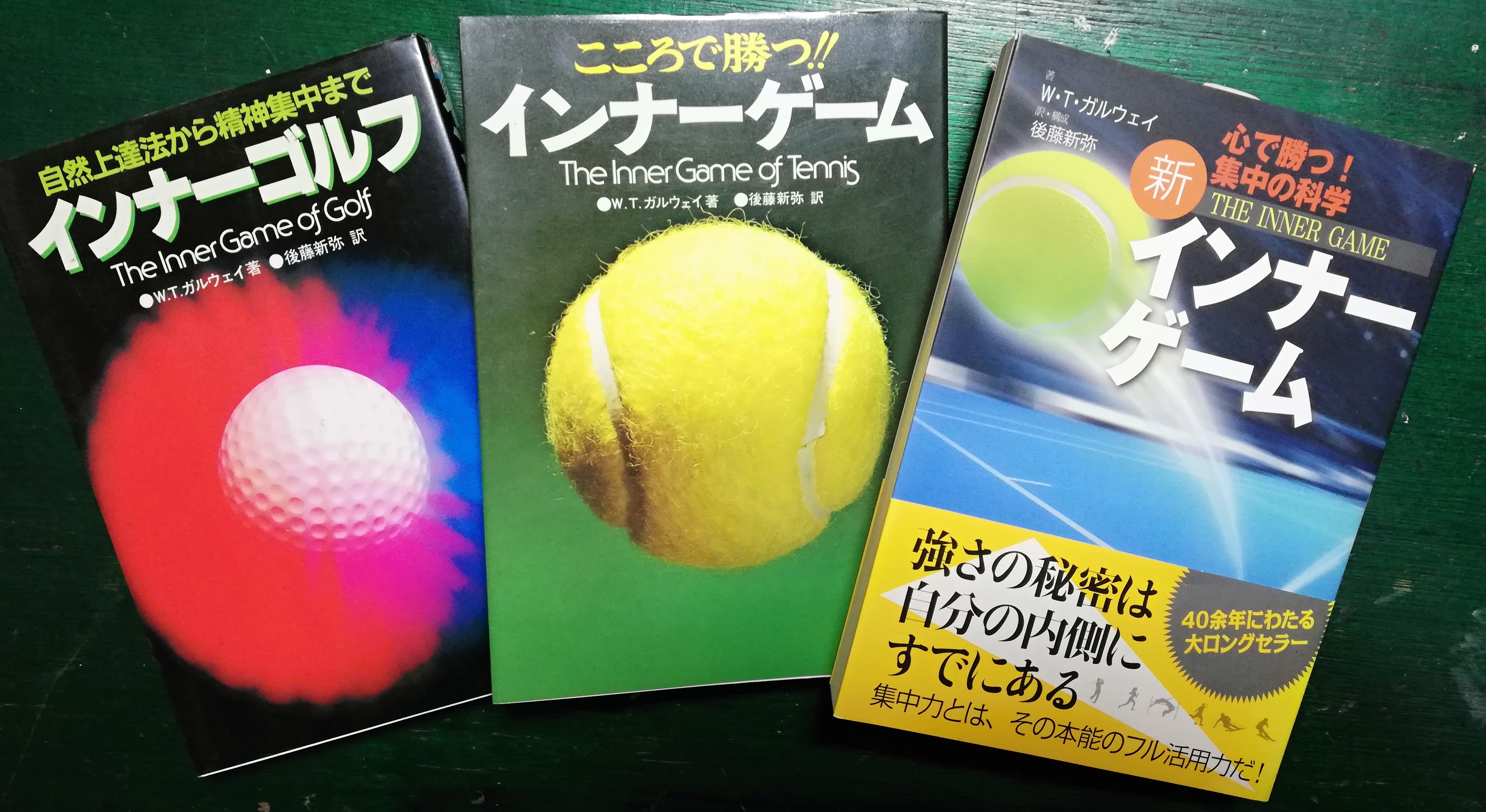
sports@js2.so-net.ne.jp
:::::後藤新弥::::
BRAVAS PHOTOS
セナがいた、プロストがいた。あの頃の撮影記録
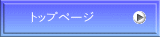
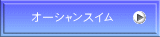
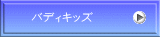
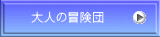
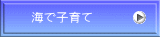
SPORTS AND ADVENTURE FOR EVERY ONE OF US
NPOバディ冒険団 & 後藤新弥(スポーツ研究室)
~NPOバディ冒険団スポーツ研究室~
プロフィール
著訳書全リスト(62冊)
おやじアドベンチャー 冒険写真集

人生の本当の意味、スポーツとは何か、逆境に挑戦するる愉快の秘密は、
すべて「集中力」にの活用に要約されるのではないでしょうか。
今年で77歳。マスコミや大学での体験をもとに、<さあ、新たな人生だ>などという意気込みなどは全くありませ。が、。NPOバディ冒険団スポーツ研究室や江戸川大学、日本レジャーレクリエーション学会などを通して「面白いこと」を続けきました。昔、「スポーツUSA]という、スポーツをおちょくった番組を古館伊智郎氏とやったことがありますが、イタズラ心は相変わらずです。サイクルスポーツの科学基地「アマンダスポーツ」のHPを担当しています。アキレス腱周囲の故障で「年だから治らない」と医者に宣告されていましたが、なんとか走れるようになりました。体は年相応、でも心は中学生レベル。早く大人になりたいなあ。
バディ冒険団 ホームページへ ![]()
以上
******************************************
****以下、プライベート・ファイル*****
2022・10・01
東京国立競技場(リレーフェスティバル)
桐葉会(東京教育大学附属中・高校 陸上競技部OB会)チーム
4人合計年齢 306歳 最高齢
リレービデオ
第⑦レーン(紫)第2走者

犬



以下は2代目 牡
公園で、雑誌撮影中のモデル(しほ)から声をかけられ、協力
掲載されましたが御礼は無し。
以下は初代、アッペンツェラー・マウンテンドッグ
やはりスイス生まれですがオオカミに近い原種で、
今のステラににてますが、いざとなるとすごかったです
(犬越路峠で、うどんを一緒に)

ポンコツ自慢
日本最初のパソコンNEC TK80
日本最初の?ハンドヘルド・パソコン
NEC PC8201
ヤマハの販売一号機 YA=1

これは1982年頃に改造使用したTL125
エンジン調整後、復活

1980年頃、清里辺りで遊びまくったQR50
前世紀1999年製 ダットサントラック
これが右アキレスけん周囲
黒い縦の筋が「変質して、年だから修理不能」と医師。
痛くて走れない、さあどうする(笑い)
<<2021 10月、レストアに成功>

BRAVAS PHOTOS
あの頃の撮影記録
最近、最も感激した作品
大学4年生? 17歳が製作した卒業論文の発表用プレゼンビデオ